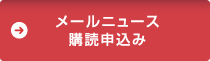Column コラム
行政経営デザインメールニュース 2025年10月
笑顔いっぱいのまちづくりに向けた市役所の組織改革(後編) ~滑川市行政経営システムの策定・定着に向けた歩み~
富山県滑川市副市長の柿沢です。
滑川市で取組んだ市役所の組織改革について、先月の続編を 紹介させていただきます。 後編では、副市長就任3年目に取組んだ行政経営システムの策定についてです。
1 行政経営システムの策定
総合計画を改定したものの、組織を動かす仕組みづくりに取組まなければ、総合計画は絵に描いた餅になることは明白でした。そこで、2024年度は、総合計画の目標達成に向けた市役所組織の改革に取組むため、NPO法人自治体改善マネジメント研究会の支援のもと、再度「チーム経営研究会」を 設置しました。
今年度の検討テーマは、各階層別の役割分担を踏まえた組織の仕組みづくりにしようと考えていたことから、副市長、課長クラスだけでなく、課長補佐、係長クラスの職員も含め、8人のメンバーで構成しました。
研究会では、滑川市の組織目標とは何か、階層別役割分担とは何かということから 検討に入りました。例えば、「総合計画の将来ビジョンとは何か」、「滑川市では戦略・組織目標を定めているのか」、「階層別役割分担はなぜ必要なのか」 といったテーマです。最初のうちは、メンバーによって意見が異なっていましたし、 何のためにこんな議論をしているのか理解できないメンバーもいました。
しかし、自分の頭で考えながら検討を進めるうちに、滑川市では、これまで戦略や組織目標を明確にしておらず、自分の仕事の目標が 曖昧だったことに気づきました。そして、階層別役割分担を明確化すること、例えば、部長等の幹部職員が組織マネジメントのために実施する具体的役割を 新たに位置付ければ組織が変わりやすくなること、また、担当職員でも目標を持って取組めば、総合計画のビジョン達成に関わっていけることに気づきました。
そして、総合計画の将来ビジョン達成に向け、目標(市長経営戦略、部長経営戦略、 課の組織目標、職員ごとの目標)を設定し、それを人事評価につなげるようにしました。さらに、これまでの事業評価に加え、新たに政策評価を導入し、 その結果を翌年度の予算編成に繋げ、実際にPDCAを回す仕組みとしました。
今、研究会のメンバー一人ひとりは、自分たちがつくったシステムに自信を持ち、なんとか組織に浸透・定着させていきたいとの思いを持っています。そうした思いから、自然発生的に、研究会のメンバーによる、 行政経営システム・サポートチームができました。今では、このサポートチームが、システムの浸透に向け、職場の上司である部長・課長等を含め、 職員に対し指導を行っています。
2 滑川市の行政経営システムのポイント
ここで、私どもがつくった行政経営システムのポイントについてお話ししたいと思います。
(1)「階層別役割分担」を定めること
市長、部長、課長、係長、担当者等の役割分担を明確にすることが システムを円滑に運用するための基本となります。この考えのもと、まずは中長期的な視点で市長が「市長経営戦略」を年度初めに策定し、部局長はそれをふまえて「部局長経営戦略」を策定する。課長は、部局長経営戦略をふまえ、当該年度の「課の組織目標」を作成し、個々の職員は、組織目標達成に向け、「個人目標」を作成する。その個人目標の達成状況に応じて、人事評価を行います。
そして、各階層の職員が戦略・目標を作成する場合、 各々の上下の階層の職員と協議し作成します。こうしたことの結果、 市長から担当職員までが背骨が通ったように一つの繋がりで結ばれることになります。これらは、すべて総合計画の将来ビジョン達成に結びつけられます。担当職員一人ひとりが総合計画の目標に向けて取組んでいる実感を持つことができます。
そうは言われるけれども、どこの自治体でも事務分担表を定めていますよね、との疑問を持たれるかもしれません。しかし、事務分担表は担当者レベルの役割は 示していますが、各階層、特に管理職の役割を記していません。そこで、 行政経営システムでは、例えば、部長の役割分担としては、部の総括といった 曖昧なものではなく、部長経営戦略の作成・市長との協議、課長が作成する組織目標についての課長との協議、政策評価の作成・市長との協議などです。 管理職は、部下の仕事の進捗管理をするだけの役割ではないのです。
(2) 幹部経営会議の設置・運営
行政経営システムを動かすためのエンジンとして、「幹部経営会議」を設置し、毎月、開催しています。幹部経営会議のメンバーは、市長、副市長、教育長、そして各部局長から構成され、民間企業で言えば経営全般を担う取締役に相当します。基本となる議題は、各部局長が定めた部局長経営戦略の進捗状況の報告・課題対応であり、他のメンバーが、自分の所管部局だけでなく、市の経営全般について意見提案します。
これまでは、部局長は、他の部局の懸案事項・課題について、あまり関心がなかったのですが、今後は、広い視野で物事を考え、また責任感も 増してくると思っています。また、部局長は、毎月の会議での報告に向け、 戦略の進捗状況の把握、課題対応に取組んでいくことになりますが、部局長が動けば、課長、係長、担当職員と、順番に波及していきます。 実際に、部局の戦略に位置付けた取組への対応が著しく進んでいると 実感しています。
(3) サポートチームの設置
行政経営システムの運用・浸透を進めるための「サポートチーム」を設置しています。 サポートチームのメンバーは、このシステムをつくった「チーム経営研究会」の8人で、副市長、部局長、課長、課長補佐、係長といった階層のメンバーです。このため、例えば、部長の役割分担である部局長経営戦略や政策評価の作成にあたり、係長級の職員が、部長にアドバイスするといったことも出てきますが、 こうしたことが普通にできています。
以前、滑川市役所の組織と職員の関係性について民間企業に調査してもらったことが ありましたが、その結果、滑川市役所の職員同士は上下の階層に関係なく、 比較的フラットな関係性であることがわかりました。このことは、これまでは職員同士の馴れ合いで仕事が進まないといった悪影響があったと思いますが、今後は、システムを運用するにあたって、このサポートチームの役割が ポジティブな効果を発揮することにつながっていると思っています。
(4) 進化する行政経営システム
この行政経営システムの運用にあたっては、職員のシステムへの習熟度を見ながら、 よりレベルの高いシステムにバージョンアップしていく、または改善していく ということを前提としています。最初から複雑、精緻なシステムを作ったとしても、職員の戸惑いが大きくなりすぎ、システムへの対応不全、様式への記入だけなど形式的な対応になることが懸念されます。
また、システムを運用していると、もっとこうしたほうが良いのではないかといった、失敗から改善案が出てくることがあります。これを柔軟に取り入れていくことも 大事です。このシステムの運用により、職員のアイデアを活かすことができるようになった、仕事が楽しくなったと思ってもらえるシステムにしたいと思っています。
次回は、番外編として、一緒に「チーム経営研究会」に取組んだメンバーの 変化について、メンバーの声をご紹介させていただきます。
▼第5次滑川市総合計画(ご参考)
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/shisei/9/11/9147.html
▼2026年度「チーム経営研究会」のご案内はこちら
https://jichitai-kaizen.net/topics1
富山県滑川市 副市長 柿沢 昌宏