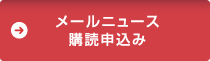Column コラム
行政経営デザインメールニュース 2025年05月
県が実践する地域企業支援の可能性 ー栃木県チーム・イノベーション実践プログラム
栃木県にてサービス産業の生産性向上のためのプログラムを、数年に渡って担当させていただいている。手前味噌だが成果はなかなかのもので、参加企業の多くが期間中に業績を向上させている。生産性向上のお手本と言える状態になってきた企業もある。栃木県ホームページに「チーム・イノベーション」の事例集が公開されているので、ぜひご覧いただきたい。
このコラムでは、栃木県チーム・イノベーション実践プログラムの起点をつくった人の想いや主管の経営支援課の陰の努力を報告する。皆様が取り組む地域企業支援へのヒントとなれば幸いである。
「県民視点・未来起点」:プログラムを構想した出発点
地域企業の経営の新しい取組を支援するための補助金は言うまでもなく大切。経営革新計画の立案は変化を構想する好機になりうる。 十分には知られていない名品を地域ブランドとして表彰できれば、県内外での認知度向上に役立つ。しかし、これらの施策が、一瞬の盛り上がりをつくるだけなら、県が支援する意味は薄くなる。大切なのは、県民に愛される企業をめざしての持続的な進化・発展の後押しである。
栃木県 経営支援課Aさんは本質的な企業の変革支援を模索していた。5年前のこと、詳細までは覚えていないが、私はお話を伺いながら 「県にこんな職員の方がいるなんて、すばらしい」と驚きにも似た感動があった。Aさんの話はいつも県民視点、未来起点だった。 背景に25年前に就職するときに定めた「私は、栃木県民の未来にどう役立てるのか、絶えず考える」というお父さん譲りの視座と決意がある。
Aさんの仕事は、県庁舎のリニューアルでも、県産品の直売所を新設するときも、県内起業家のための支援プログラムをつくるときも、常に成果は未来の県民を意識したものになる。もちろん、本プログラム「栃木県チーム・イノベーション実践プログラム」も県民の豊かさにつながることが軸である。参加企業の商品・サービスが磨かれた結果、県民の暮らしがより豊かになる。同時に、地域企業で働く人の働きがいも給与も上がる、本質的な変化をねらって、プログラムを構想した。
「9か月間でやる」:挑戦でもあったプログラムの設計
私は、Aさんの想いを次のように受けとめた。
(1)参加企業の瞬間的ではない、持続する変化をつくる。
(2)参加企業10社に栃木県内のDXを含んだイノベーションの流れをリードするコアメンバーになっていただく。
(3)モデル企業をつくり、そこから生きたメソッドを発信する。
(4)これらを9か月間のプログラムで実現する。
我々が通常、支援している企業風土改革プロジェクトで考えると、9か月間は短い。少なくとも一年半はかかるだろうことを約半分の期間で行なおうというのである。依頼元のリクエストを変化のチャンスと捉え構想した。「栃木県チーム・イノベーション実践プログラム」は、支援者である私たちにとってもイノベーションの機会であった。
9か月間での生産性向上と働きがいの同時実現のグランドプロセスは「一品」を探して、伸ばして、広げること。その中で、ぶどうが熟成して、ワインになるように、自社の得意技能を掘り起こして発展的な形態へ、価値の飛躍をめざす。新商品開発がイノベーション、新しいことをやることが生産性アップと主張する人もいる。それらの手法とは異なる、すでに自社にあるもの、既存のものを足場に、顧客に向けて価値を伸ばし、伝えるトライを日常の仕事にしていくことをプログラムの核にしている。
チームで参加する8回の商品・サービスの改良ワークショップと同時に強化したのが、参加企業との現地での作戦会議である。集合する場よりも、現地で行なう作戦会議の回数がより多いことが本プログラムの特徴でもある。臨機応変に、各社の変化をつくりだすことに注力しなければ、「勉強しました」「ためになりました」で終わってしまう。かつての大分県一村一品の成功には 現地に出向くコーディネーターの存在が大きかったと聞いている。我々も同様に現地、現物、現場での取組を大切にしている。
「他社と協働で取り組む」:プログラムのサブエンジン
参加企業同士、全体が大きなチームになるように支援する。県のメンバーと我々、商工団体の指導員の方もチームになるように。いつでも相談にのってもらえる指導員の存在は、プログラム終了後の持続的な変化を支える。県が企画するイベントに企業が参加し、売上や認知度のアップにつなげる。一社では解決しにくいことも、複数社で組んで解決しようとする場面を増やす。
9か月間のアウトプットは、参加企業の商品・サービスの革新だけに留まらない。地域での連携・協力・相談関係の質を高めることにも注力して「栃木県チーム・イノベーション実践プログラム」を展開している。
県民の日イベントへの出店、企業の垣根を越えた協働販売、互いの持ち味を生かしながら売上アップに協力する取組が、徐々に増えていくのも、横で見ていて嬉しい限り。誰でもいつものメンバーといつものように考えていれば、同じことの繰り返しになってしまうものである。
変化の敵はマンネリである。困ったとき、新しいことにトライしようと思うとき、気軽に相談しあえる異業種の方々とのつながりは、見えない財産として効いてくる。地域企業同士のネットワークが、ひとつの商店街のように商売に取り組んでいくこと。栃木県 経営支援課Aさんが意図した持続的な変化を支えるサブエンジンが機能している。
「一社一品」:プログラムのさらなる可能性を切り拓く
現在プログラムは、発起人Aさんから、後任のBさんへ引き継がれた。Bさんはこれまでのプログラム参加企業である 40社を県内企業の生産性向上をリードする基盤と捉えて、新たなアイデアを加えて発展させようとしている。県内企業の生産性アップのためのスローガンを「一社一品」として、さらなる展開を模索しているのだ。生産性と働きがいの向上のための突破口である「一品」、ぶどうをワインのように熟成させてきた「一品」を、各社が持ち、磨いている、そんな状態をねらう。
具体的には、過去参加企業のプログラム期間後の取組もメソッドにまとめて、プログラムに参加していない企業の方々にも伝えるオープンセミナー。年度をまたぐ企業間の連携で、刺激をしあいながら、変化を促すプラットフォームに、県が自らなっていく取組。県のイベントを通じて、各社の「一品」である商品・サービスを県民の方々に伝える場などだ。
県が地域企業の経営支援を行なっていくことの可能性を私は次のように感じている。県内事業者をひとつの商店街として活性化できる支援機関になりえる。損得なしでサポートできる中立性が県民に大きな安心感を与え、公平な判断で県民にとってのいいものにフラグを立て、県全体の商品・サービスレベルを高めることに影響を与えうる。非常に大きな可能性である。
Bさんとの取組はまだまだ道半ばであるが、皆様にいい報告ができるように、栃木県で人々が働くこと、生活をしていくことが、これからの日本の課題解決の一つの モデルになる状態を目指していきたいと強く思う。
昨年度、このプログラムに参加した鹿沼カントリー倶楽部のマネージャーと 若手メンバーの格闘もスコラのコラムでご紹介しています。
▼コラムの詳細はこちら
https://www.scholar.co.jp/column/id=15626
▼令和6年度栃木県 チームイノベーション実践プログラムはこちら
https://www.scholar.co.jp/case/id=15469
プロセスデザイナー 岡村 衡一郎