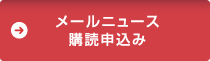Column コラム
行政経営デザインメールニュース 2025年04月
公務員の組織風土改善成果報告<部署連携・公民連携編>より
NPO法人自治体改善マネジメント研究会では、政策、施策を推進していくうえで抱えている課題を解決していくために、仕事と人の両面からアプローチする「組織風土改善セミナー」を開催しています。
セミナーは、半年を1クールとしていますが、参加者のほとんどは通年で継続参加し、年度末に実践者の一部メンバーが、成果をオープンに共有する機会を設け、所属する自治体の内外に活動の輪を広げていこうとしています。
今回ご紹介する事例は、発表者4人のうち部署連携・公民連携の課題解決に取り組まれた2人の事例です。
報告会に参加しそびれた方は、NPO法人のHPにて発表部分のみ視聴が可能です。
▼発表事例の動画はこちら
https://jichitai-kaizen.net/news/1216
▼発表者が報告会に先立ち、事前発信したメッセージが掲載されているコラムはこちら
https://gyousei-design.jp/column/2025/02/post-158.php
▼前回紹介した<職場編>の2事例の概要を掲載したコラムはこちら
https://gyousei-design.jp/column/2025/04/post-159.php
【報告3】 西川 展子 (にしかわ のぶこ)
和歌山県 教育庁生涯学習課長
「教育と福祉の連携~カタリバチャレンジ2022-2024~」
<概要>
きっかけは教育長から「教育と福祉、一緒になって子育て世帯を支援できないか?」との問いかけに、「両部局の職員が同じ目的のもと、チームとして一緒に動きたい」との思いを持ち、「両部の間の壁は何だろう?」「将来どういう状態になればいいのだろう?」を 探るためにオフサイトミーティング(対話の場)を取り入れた「カタリバ」をスタートさせた。
<3年間の取組と得られた成果>
・初年度は関係4課参加者8人の仲間づくりに孤軍奮闘し、ジブンガタリ、モヤモヤガタリから生まれる相互理解から教育と福祉のお互いの認識に溝があること、それを改善して「のりしろを重ね合えば可能性が生まれる」連携がありたい姿だとわかり、課題と目的が明確になった。
・2年目は関係7課参加者約20人になりカタリバ運営を相談できるコアメンバーもできてきた。
参加者の間では「意見を交わす、聞く、聞いてもらうことが楽しい!」と感じ、参加者同士のつながりができはじめた。2つの事業で教育と福祉の接着点を共有でき自発的な動きも出始めたことで具体的な実践のアイデアが描けた。
・3年目には関係9課参加者約30人に増え、小学校や県立高等学校、市町村役場などで、現場の協力を得て、教職員、福祉関係者、家庭訪問支援員等色々な立場の方々が一緒に事例検討を通して様々な意見を語り合うことができた。
カタリバを通じての取組は、知事も出席する総合教育会議の場で進捗報告でき、取組のスポンサーとなる部局長同士の顔合わせや 打ち合わせも開催したことなどが取組への追い風となっている。
<見どころ>
西川さんの取組は、部局の壁を、互いの「のりしろ」を伸ばし、カタリバでの対話で「重ねていく」ことによって接着点をつくり乗り越えていくものでした。
「カタリバ」という対話の場を設定して、孤軍奮闘の時期もありましたが、迷走も仲間との信頼関係で乗り越えて対話と小さな実践によるプロセスを積み重ね、トライアンドエラーを繰り返しながら教育と福祉の接点を実現したものです「カタリバ」でつながった多くの人の関係性は、今後いろいろな場面で生きてくるものと思います。
【報告4】 溝口 尚也 (みぞくち なおや)
人吉市 復興政策部長
「復興まちづくりの具現化のために~フォーマルとインフォーマルの多重奏的取組~」
<概要>
2020年の豪雨災害からの復興まちづくりを進めるために策定された、復興まちづくり計画、まちなかグランドデザイン推進方針を具現化していく取組で、令和6年度は行動指針となるアクションプランの策定と公民連携でデザイン会議を運営し、令和7年度から社会実験を実施、その後民間投資・活動と連動したハード整備と民間担い手による各種事業をスタートさせていくもの。
そのため、これからのまちづくりのためのビジョンからハード整備への視点を、従来の行政で行っていた「つくる目線」(つくれば使うマスタープラン主義)ではなく、事業や活動を行う「つかう目線」(使われるものをつくる事業性主義)に変えることにした。
<ポイント>
国、県、市、専門家、学識経験者、地元民間事業者が参画するデザイン会議や その下に設ける、市、民間事業者、団体、個人が参画するいくつものタスクフォースは 組織文化の異なる主体の集まりであることから、シームレスな運営には コーディネート機能が必要であり、専門家、民間事業者と、 まちづくりの目的とビジョンを共有し、フラットな関係性で連携していくには 市職員の公民連携への理解を深めマインドチェンジしていく必要も感じたことから、 デザイン会議の前後には本音で話せる環境を整えて、全体調整のための少人数会議をオンラインも活用しながら何度も設定し、タスクフォースでは主たる運営担当の中堅若手職員をコーディネートチームが 支援をした。
<得られた成果>
アクションプランの策定、デザイン会議が機能しビジョンに向かうチームになってきたとの評価をいただいたことや一部タスクフォースが動き始めたこと。
タスクフォースの中堅若手職員にリーダーの自覚が出てきたこと。部長同士が経営的な目線を持って部門や立場を超えて連携しあうようになったこと。
民間事業者や専門家が介在することで、かえって庁内他部署とのつながりや連携ができてきたこと。
参加メンバー間に立場を超えて、ひとつのビジョンを元にまちづくりを考え、実行する実感が出てきたこと。
情報発信力のある民間とつながるなど、情報発信のやり方を変えたことなど。
<見どころ>
溝口さんの取組は、災害からの復興まちづくりを「公」と「民」が連携して、まちづくりの担い手となる「民」の目線(つかう目線)で進めようとするものですが、組織文化の違う「公」と「民」がシームレスに繋がるために、要所要所で果たしている実会議やオンラインでのこまめな協議・会議の場と オフサイトミーティングの考え方を取り入れたコーディネートが 重要な役割を果たしていると思います。大きな目標に向けた重要な会議の前後に少人数で、時には1on1で、目的や方向性、ありたい姿を共有し、本音で話せる場の設定を重視するオフサイトミーティングを活用して、役所の文化を抜け出し、「公」と「民」の相互理解を促進して協力関係を 築かれていると思います。
「公務員の組織風土改善セミナー」は、課題、問題を解決したいと 思っている人たちが、組織風土改善のポイントを学び、周りの人たちと共にプロセスの実践を通じて解決を図っていくことを目的としています。
【基礎コース】では、改善に向けた基本的なチェックポイントの理解と 改善への取組の第一歩を踏み出す場づくりをし、
【実践コース】では職場で実際の動きを創り出しながら 継続的な学習を通じて改善力をアップし、課題を解決していきます。
今年度の仕事をスタートするにあたり、仕事の仕方を見直したい、職場のチームワークを良くして組織風土を改善・改革したい、地方創生やDXなど新たな課題にチャレンジしたい、他部署や他機関、 公民の連携・協力関係を築きたいと思われている方は、先ずは本セミナーの基礎コースからご一緒に取り組んでみませんか。
申し込みを開始していますので、ご参加をお待ちしています。
▼「公務員の組織風土改善セミナー」【2025年度上期 基礎コース】の申し込みはこちら
https://peatix.com/event/4320217
NPO法人自治体改善マネジメント研究会会員 小山 巧(元三重県職員、元三重県病院事業庁長、元南伊勢町長)