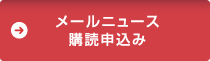Column コラム
行政経営デザインメールニュース 2025年01月
年初の首長のメッセージは、いかがでしたでしょうか
年初には、おそらくほとんどの自治体で 首長が職員向けにメッセージを出されていることと思います。それはどんな内容だったでしょうか。
実は、私が組織風土改革のコンサルティングをする中で、最も重視している取組の一つにこの年初の首長メッセージに関する首長への作成支援があります。今日は、このようなメッセージを発信した場合に首長と職員の間にどのような効果があるのか、またその効果を高め、次年度につなげていくためのポイントをいくつか紹介させていただきます。
【1】メッセージを通じて、首長の思いを知る
職員は首長の補助機関です。 だとすれば、(1)まず初めに首長がどんな思いを持っているのかを知ることが欠かせません。また、(2)首長がその思いをもとにご自身で何をしようとしているのかを知っておくことが大切です。そのうえで、(3)首長を補助するためには、首長が職員に期待していることは何か、その期待どおりに職員が仕事していると満足しているのか、どこかに過不足を感じているのかについて把握しておく必要があります。
これら(1)~(3)は、小規模自治体や幹部層であれば、日々首長と直に接する機会が多くあり、首長の考えや思いを知ることができるでしょう。しかし、規模が大きくなると(1)の首長の思いを知ることさえままならないものです。ほとんどの職員は、幹部を通じて、もしくは、会議に同席している管理職や 管理部門の人などを介して知ることになります。それでも組織のフィルターを通すと、ろ過されてごく一部の内容しか伝わらなかったり、意味が変わって伝わることになりがちです。
それゆえ、首長が職員に向けて直接思いを発する機会はとても重要です。中でも年初や年度当初は、発信する首長にとっても、受信する職員にとっても、タイミングが定まっているため、年間スケジュールの中で活用方法をうまく設定しておけば、組織全体で運営効果を高められます。
【2】職場で年度をふり返る対話をしっかりして、組織学習する
年初は、今年度の仕事のめどがほぼ立って来た時期にあたり、事業・業務について新たに指示・命令を出す必要性は薄れているかもしれません。その半面、今進めている仕事に関して職員が最も精通している時期にあたり、関係者とのつながりも深く、相互の強みや弱み、可能性や課題を熟知している状況にあります。
そこで、年初から年度末にかけての四半期には、今年度の事業・業務について業績結果を評価するだけでなく、その理由がどこにあったのかを関係者と一緒にしっかり対話してふり返れば、要因を掘り下げてとらえることができるはずです。
次年度の予算もほぼ固まって来ていることから、大きな方向性のめども見定められているため、それをどうやって推進していけばよいのかの具体的な改善策についても検討しておけば、次年度の取組が進めやすくなるでしょう。互いに気心知れた間柄になっている関係性を生かして、ぜひ多様な視点からアイデアを出し合っておきましょう。
実行した人の創意工夫は、上司と部下の人事面談の中で、個人目標にあれば評価されるものの、内容は秘匿されています。そのため、関係者全員に関わる組織としての仕事のやり方、働き方など、「組織力」や「生産性」を左右する重要なノウハウが意外と個人の暗黙知のまま共有されずに終わっているのです。そこで、あらためて機会をつくってふり返り、対話してノウハウを共有し、改善の知恵を出し合う組織学習をしておくことが重要です。
首長の年初のメッセージでは、年度末に施政方針を発信する前段階で、これら年度のふり返りを全部署で行ない、次年度の施政に向けてどのような 改善を準備しておいてほしいのかの組織運営の方針が発信されていると、職場でふり返る対話が進めやすくなります。
【3】組織の一体感をつくり、次年度に向けて助走をスタートする
行政組織では、新年度になると何割かのメンバーが入れ替わり、チームワークがリセットされてしまいます。「組織」として、効率的に仕事を進め、効果的に成果を出していけるようにするためには、このデメリットをいかに軽減できるかが課題となってきます。行政評価には前年度の業績結果や次年度の業績目標は記されていますが、次年度の改善方法まで具体的に詳述しているシートはめったにありません。
そこで、【2】のふり返りをもとに、担当者は業務遂行に必要な能力向上の課題や 育成方法の案を作成し、管理職が次年度の「組織目標」の素案に これらのポイントを記して用意しておくことが肝要です。管理職の「組織目標」が職場のマネジメントの引き継ぎ書として活用できれば、 もし異動があったとしても、組織全体で新年度の新体制のもとでも何に注力するのかのポイントや、仕事を進めるうえでの姿勢について年度当初から共有することができ、チームワークを図りやすくなります。
さらに、この「組織目標」には、やることだけでなく、組織がチームとなるための目標も記されているとより結束力が高まります。
たとえば、青山学院大学の原晋監督は、箱根駅伝に出場するにあたり毎年 「ハーモニー大作戦」「パワフル大作戦」など「〇〇大作戦」といった標語をもとに選手を鼓舞しています。これは、その年が自分たちにとってどんな意味を持つのか、何に注力していけばいいのかを象徴する言葉になっており、これを合言葉にしてメンバーが力を合わることにつながっています。
自治体の首長は、4年の任期がありますので、1年ごとにかける思いを明確に持っていることでしょう。それを標語にして職員と共有すれば、役所全体で共通言語ができ、息を合わせやすくなります。 また、それが総合計画基本構想の理念とつながり、将来像の達成に向けた道標となっていれば なお意義深いものとしてとらえやすくなります。
次年度がスタートすれば、これを職場ごとに具体化したり、アレンジして設定し直すように展開していくことによって、トップから現場の第一線の職員までが本気になれる意味と価値を共有し、組織全体で一体感を持って志気を高めていくことができるでしょう。
みなさんにとって、これから年度末にかけての期間が、効果的な組織学習の期間となり、次年度に向けてエネルギーを高めていく助走を 始められますことを願っています。
行政経営デザイナー/プロセスデザイナー 元吉 由紀子